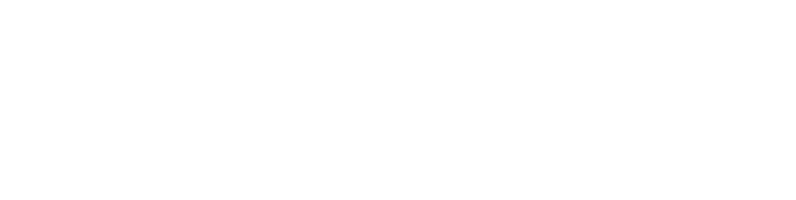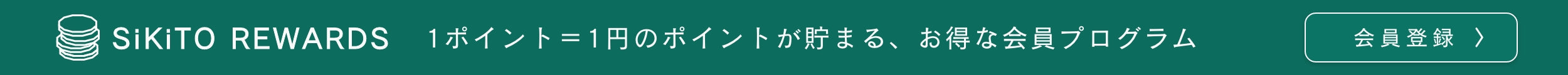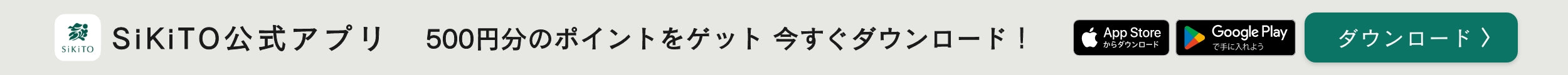【二十四節気】
芒種(ぼうしゅ)

芒種(ぼうしゅ)
6月5日〜20日頃
梅雨の気配が濃くなり、空模様がめまぐるしく変わる「芒種(ぼうしゅ)」の頃。
毎年気になる梅雨入りの時期ですが、平年だと九州が6月4日頃、四国が6月5日頃、中国〜東海が6月6日頃、関東甲信が6月7日頃といわれます。
「芒(のぎ)」とはイネ科の植物の先端にある棘状の突起のこと。芒のある穀物の種を蒔くのに適した時期とされますが、実際にはすでに田植えが本格化しており農村では苗植えが忙しい時季でもあります。
紫陽花など、しっとりと濡れた地面に咲く花の姿には梅雨ならではの美しさがあります。次の節気は「夏至」。いよいよ夏が始まります。
七十二候
6月5日〜9日頃「蟷螂生(かまきりしょうず)」

初夏の陽気に誘われて、かまきりの子どもが土の中から出てくる頃。
草むらでは小さな昆虫たちが動き出し、かまきりの鋭い目がきらりと光ります。まだ頼りなさを残しながらも、しっかりと鎌を構えるその姿には、野生のたくましさと自然の摂理が垣間見えます。
6月10日〜15日頃「腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる)」

草が腐って蛍になる、という詩的な言い回しに、昔の人の自然へのまなざしが映ります。
実際には湿った草むらや水辺に蛍が舞いはじめる頃。夕暮れどき、水辺にふわりと浮かび上がる小さな光は、梅雨の訪れとともにやってくる幻想的な風景です。
かつては夏の風物詩として親しまれ、蛍狩りを楽しむ人々の姿も各地で見られました。儚くも美しいその光に、ひととき心をゆだねたくなる季節です。
6月16日〜20日頃「梅子黄(うめのみきばむ)」

梅の実が黄色く熟しはじめるころ。
春に花を咲かせた梅が、たっぷりと雨を吸って丸く膨らみ、やがて収穫の時を迎えます。この時季に収穫された青梅は、梅酒や梅シロップ、梅干しへと生まれ変わり、夏の保存食として重宝されます。
台所に並ぶ青い実と、氷砂糖や塩の透明な輝き。梅しごとは、初夏ならではの手仕事として、日々の暮らしに季節のリズムを刻みます。
旬の味わい、行事など
芒種の頃は、初夏の野菜がますます充実してくる時期。
ピーマン、ズッキーニ、とうもろこしなどが旬を迎え、食卓にも夏らしい鮮やかな色が増えていきます。

シンプルに蒸したり焼いたりするだけで、野菜本来の甘みや力強さを感じられる季節。塩茹でするだけでも旬の滋味がしっかりと味わえます。
魚では、鱧(はも)やイサキ、太刀魚などが旬。特に関西では、梅雨の時期に脂がのってくる鱧が「梅雨の味」として重宝されます。骨切りされた鱧を湯引きにし、梅肉や酢味噌でさっぱりといただくのが風雅な楽しみです。

「芒種」まとめ
芒種は、空気も大地も、ひたひたと夏へと歩み始める頃。
梅を漬ける、蛍を見る、雨を眺める──そんな些細な行いのなかに、暮らしの豊かさが潜んでいます。
芒を持つ種が大地にまかれるように、私たちのなかにも新たな種がまかれ、やがて芽吹いていく。
そんなことを、そっと教えてくれる節気です。
PRODUCTS