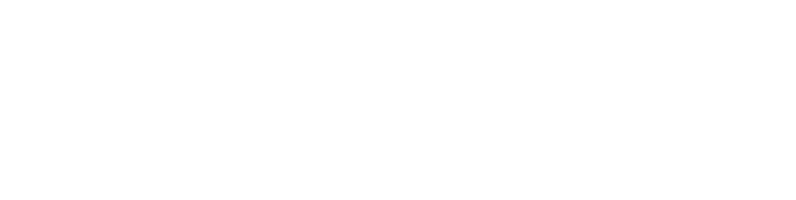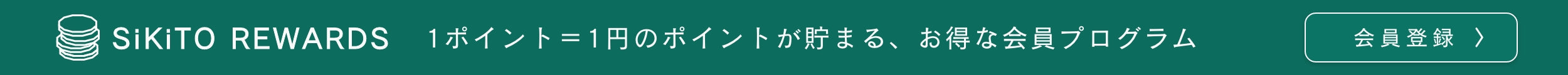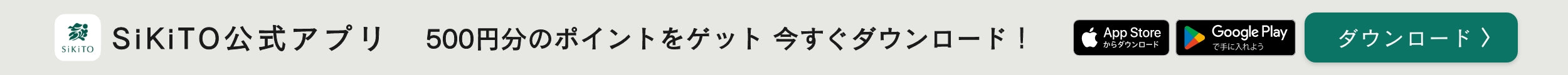【二十四節気】
夏至(げし)

夏至(げし)
6月21日〜7月6日頃
1年のなかでもっとも昼が長い「夏至(げし)」。
高く昇った太陽から力強い日差しが降り注ぎ、地上のすべてが陽の恵みをたっぷりと浴びています。
と同時に梅雨の真っただ中でもあるので雨も多い時期。晴天と雨天が交互に訪れる不安定な様子もこの季節ならではの表情です。
湿った空気がじっとりとまとわりつく日もあれば、抜けるような青空の下で緑が輝く日もある。季節は確実に夏本番へと向かっています。
七十二候
6月21日〜25日頃「乃東枯(なつかれくさかるる)」

「乃東(なつかれくさ)」とは、ウツボグサのこと。夏に枯れることから名付けられたとされます。
晩春から初夏にかけて紫色の花を咲かせ、夏至の頃になると静かにその役目を終える姿に生命の循環を感じさせます。盛夏に向かう時期にひとつの花が枯れゆく姿はどこか涼しげで、心を鎮めてくれるようです。
6月26日〜30日頃「菖蒲華(あやめはなさく)」

湿地帯に菖蒲(あやめ)の花が咲き誇る頃。
紫、青、白の繊細な花びらが風に揺れ、梅雨空の下でも凛とした存在感を放ちます。水辺に咲くその姿には、雨の多い季節ならではの風情があります。
あやめ、しょうぶ、かきつばた。よく似た花々が織りなす景色の中に、日本人の自然観が息づいています。
7月1日〜6日頃「半夏生(はんげしょうず)」

半夏(からすびしゃく)という薬草が生えはじめる時期。
農作業の節目ともされ、関西地方では田植えを終えたことを祝ってタコを食べる風習もあります。タコの足のように稲がしっかり根を張るようにという願いが込められてきました。
また、ハンゲショウ(半化粧)という植物もこの頃に花を咲かせます。白く染まった葉が目をひく涼やかな姿で、梅雨時の庭先に彩りを添えてくれます。
旬の味わい、行事など
夏至を迎える頃、お店には本格的な夏野菜が並びます。
トマト、ナス、きゅうり、ピーマン、とうもろこし。色とりどりの野菜たちは、見ているだけでも元気をもらえるよう。陽を浴びて育ったその味は濃く、火を通しても生でも、その力強さを感じさせてくれます。

海の幸ではイワシが旬を迎えます。梅煮やつみれにするとさっぱりとした味わいで包み込んでくれます。くせのない白身魚もおいしい時期で、加熱しても身がふっくらとやわらかく仕上がります。

夏至の日には、世界各地で太陽を祝う行事が行われます。北欧では白夜を祝う祭りがあり、日本でも「暑さに向かう心構え」をするような風習がありました。
農村では「半夏生」までに田植えを終えるのが通例とされています。
「夏至」まとめ
太陽がもっとも高く昇る夏至は、陽の力が大地全体に満ちるとき。
空は晴れるばかりではなく、時に激しい雨が降り、雷鳴が轟く日もあります。そんな気まぐれな空模様のなかで、植物も人も、ぐっと背を伸ばして季節に順応していくようです。
じめじめとした空気のなかにも、光の兆しを見つける目を持つこと。雨の音に包まれながら、ふと深呼吸してみること。
それは、梅雨を健やかに過ごすためのささやかな知恵かもしれません。やがて訪れる真夏に向けて、自然も人も静かに準備を進めています。
陽がもっとも長い日、ひととき空を見上げて、太陽のぬくもりを全身で感じてみませんか。
PRODUCTS