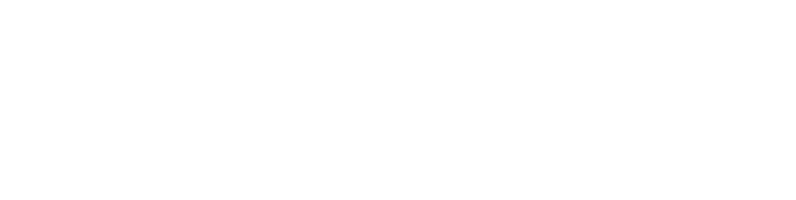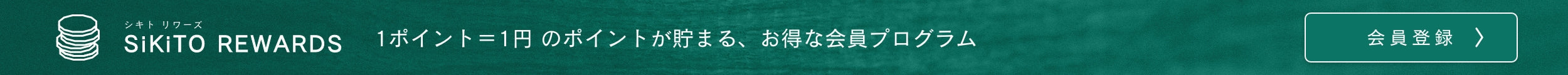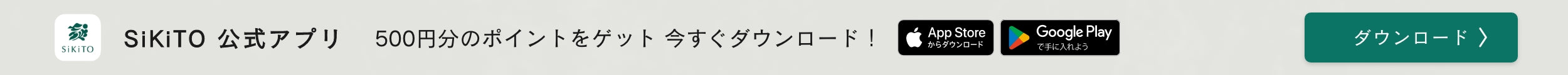バイオフィリックデザインとは?|取り入れるメリット・インテリア例

バイオフィリックデザインとは、オフィスや自宅に自然の要素を空間に取り入れることで、人の健康や幸福感を向上させるデザイン手法のことです。
本記事では、バイオフィリックデザインとは何か、メリット・デメリット、取り入れ方や注意点などについて紹介します。
バイオフィリックデザインに興味がある方、緑のある暮らしに憧れている方はぜひ参考にしてみてください。
バイオフィリックデザインとは?

バイオフィリックデザインとは、自然の要素を空間に取り入れることで、人の健康や幸福感を向上させるデザイン手法を指します。
バイオフィリックデザインを取り入れるうえで深く関係しているのが、1980年代にアメリカの生物学者エドワード・O・ウィルソンによって提唱された「バイオフィリア(Biophilia)」という概念です。彼は「人間には本能的に自然とつながりたいという欲求があり、自然と触れ合うことで健康や幸福を得られる」と考えました。
この理論に基づいて「建築やインテリアに自然の要素を取り入れることで、人々がより快適に過ごせる環境をつくる」と考案されたデザインが、バイオフィリックデザインです。
実際に、東京農業大学教授・水庭 千鶴子(みずにわ ちずこ)先生が、緊張状態を示すRPP値(Rate Pressure Product)[*1]を用いて、歯科診療室に植物や花があることで緊張緩和に効果があるかを調べました。
①植物や花がない場合、②植物のみがある場合、③植物と花がある場合でのRPP値を測定したところ、
①植物や花がない場合>②植物のみがある場合>③植物と花がある場合
となり、このことから、植物や花による緊張緩和の効果が示されました[*2]。
東京農業大学教授・水庭 千鶴子(みずにわ ちずこ)先生の研究については、以下の記事でさらにくわしく紹介しています。

四季を運ぶ枝ものは、家の中の『庭』になる
よみものはこちら 〉
[*1]RPP値が高いほど緊張状態といえる
[*2]論文「緑化が被検者に与える緊張感の変化 -歯科医診療室を事例として-」 水庭千鶴子・阿藤舞・近藤三雄 東京農業大学農学集報 第53巻第2号(2008)
バイオフィリックデザインを取り入れるメリット
バイオフィリックデザインを活用することにより、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここからは、オフィスや住宅にバイオフィリックデザインを取り入れることで期待できるメリットを紹介します。
ストレス軽減やリラックス効果を得られることがある
バイオフィリックデザインを取り入れることで、ストレスの軽減やリラックス効果が期待できます[3*]。
農林水産省では、「花のある部屋で過ごす人は、ストレス時に高まる交感神経の活動が25%抑えられる一方、リラックス時に高まる副交感神経の活動が29%高まることがわかっており、花の癒し効果が医学的にも証明されている」と発表しています[4*]。
現代社会では、パソコンやスマートフォンの多用により脳への負担が大きくなりやすく、心身のリフレッシュが欠かせません。植物などの自然に囲まれた環境に身を置くことで、心拍数や呼吸の安定が期待できます。
室内にいながら外の開放感を感じられる植物、自然光を活用することで心理的にもリラックスしやすくなり、より快適な空間が生まれるでしょう。
[3*] 四季を運ぶ枝ものは、家の中の『庭』になる
[4*] 特集1 楽しみませんか?もっと花のある暮らし/農林水産省
幸福度が高まる
バイオフィリックデザインを取り入れることで、幸福度を高める効果が期待できるのもメリットの一つです。
アメリカのロバートソン・クーパー社は、従業員が仕事で感じる「喜び」や「やりがい」(=幸福度)を数値化し、発表しました。その結果、自然と接触する機会がある人々は幸福度が最大15%上昇することが明らかになりました[5*]。
職場だけでなく自宅にもバイオフィリックデザインを取り入れることにより、幸福度の向上が期待できるでしょう。
[5*] 世界中の職場におけるバイオフィリックデザインの効果
業務の質や生産性が高まる
バイオフィリックデザインは、主にオフィスで多く活用されています。従業員の幸福度が高まると、業務の質や生産性、仕事自体のモチベーションもアップする効果が期待できるでしょう。
好きなことや趣味に没頭しているとき、時間があっという間に経っていた経験をしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
喜びややりがいなどの幸福感を感じながら仕事に取り組むことで、集中力は高まり、生産性が向上します。
バイオフィリックデザインを取り入れることは、企業の業績アップにもつながる可能性があるのです。
バイオフィリックデザインを取り入れるデメリット
バイオフィリックデザインにはメリットが多い一方、デメリットもあります。ここからは、バイオフィリックデザインを取り入れることによる主なデメリットについて紹介します。
植物の手入れが大変
バイオフィリックデザインを取り入れる際の課題の一つが、植物の管理です。
植物は水やりや剪定などの手入れが必要なため、定期的なメンテナンスが難しい場合は、専門業者に依頼するのも1つの手段といえるでしょう。自宅に緑を取り入れたとしても適切に管理されず枯れてしまっては、本来のリラックス空間を作り出せず、ストレスの原因になりかねません。
バイオフィリックデザインを活かすためには、定期的な維持管理が欠かせない要素といえます。
レイアウトの配慮が必要
バイオフィリックデザインを導入する際は、安全面や動線を考慮したレイアウトが不可欠です。
床に置くと転倒のリスクが高まるほか、吊り下げ型の植物は落下する危険性もあるでしょう。
また、通路や出入り口付近に植物を配置すると移動の妨げになるるため、レイアウトには十分な配慮が必要です。
バイオフィリックデザインを取り入れる際のポイント
バイオフィリックデザインを取り入れる際は、いくつかのポイントを押さえる必要があります。中でも重要なポイントを紹介します。
メンテナンスが簡単なものを選ぶ

バイオフィリックデザインに取り入れる植物は、メンテナンスが簡単なものを選ぶのが理想的です。手入れが難しい植物を選ぶと、水やりや剪定が負担になってしまい、最終的に枯れてしまう可能性があります。
維持管理の手間を減らしつつ、空間に自然の癒しを取り入れることが重要です。そのため、バイオフィリックデザインには育てやすい植物を選ぶことがポイントといえるでしょう。
自然光を活かす

植物を置く際は、自然光を最大限活かすのも重要です。自然光を取り入れるためには、窓の配置を工夫し、室内に十分な光が届くようにしましょう。
また、カーテンやブラインドを調整することで、日光が差し込む時間を増やし、明るく開放感のある空間をつくれます。
天然素材を取り入れる

バイオフィリックデザインに天然素材を取り入れることで、温かみと落ち着きのある空間を作り出せます。
家具、床、壁材に、木材や竹を使用することで、自然の風合いや質感を感じられるでしょう。また、リネンやウール、コットンなどの天然素材を取り入れることで快適さが向上し、空間全体に自然のぬくもりを感じられます。
バイオフィリックデザインの実例
実際にバイオフィリックデザインを取り入れている家の実例を紹介します。
壁紙に取り入れる

グリーン調で植物柄の壁紙、もしくはウッディ調で植物を引き立てるような壁紙は、おすすめのバイオフィリックデザインの取り入れ方です。
壁紙に取り入れることで視覚的に自然を感じられるため、実際に植物を配置するのが難しい環境でも自然の要素を取り入れられるでしょう。
しかし、壁紙のデザインが過度に派手なものや色が強すぎる場合は、圧迫感を与えてしまう可能性があります。そのため、家具との相性や部屋の雰囲気に合った色合いやパターンを選ぶことがポイントです。
ダイニングに取り入れる

ダイニングに取り入れられるバイオフィリックデザインは、自然の要素を取り入れて心地よい食事の時間を演出できるためおすすめです。
例として、植物をテーブルの上に置くと開放感を感じられるでしょう。特に、小さな観葉植物を選ぶことで視覚的にも癒されるだけでなく、食事の空間を邪魔せず自然を感じられます。
また、木材を使った家具や食器は、温かみと落ち着きのある雰囲気を作り出します。木のテーブルや椅子、お皿などは、自然素材の質感を感じられて植物との相性も抜群です。
ダイニングにバイオフィリックデザインを取り入れることで、食事をより楽しいものに変えられるでしょう。
デスク周りやフリースペースに取り入れる

デスク周りやフリースペースのバイオフィリックデザインは、仕事やリラックスの空間を自然の要素で心地良くできるでしょう。
例としては、観葉植物をデスクに配置することで、視覚的な癒しを感じられます。小さな植物や枝ものは手入れも難しくなく、効果的なリフレッシュが期待できます。
また、自然素材の家具やインテリアを取り入れるのも効果的です。木製のデスクや椅子、小物のインテリアを使用することで、温かみのある自然な雰囲気を演出できます。
また、自然光を取り入れるために、窓辺にデスクを配置することもおすすめです。
まとめ
バイオフィリックデザインは、自然の要素を室内環境に取り入れることで、人々の心身の健康や幸福感を高めるデザインの手法です。
オフィスや自宅にバイオフィリックデザインを取り入れることで、ストレス軽減や集中力の向上、リラックス効果が期待できます。
バイオフィリックデザインを上手に取り入れて、理想的で快適な暮らしを実現させましょう!

枝もの定期便|季節の枝ものをご自宅にお届け
商品をみる 〉
PRODUCTS