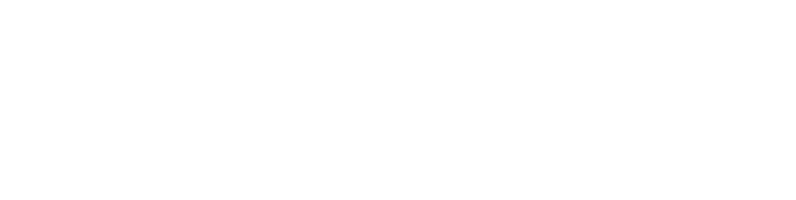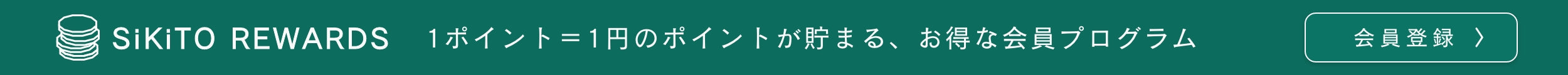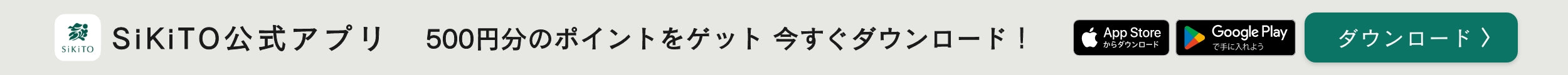紫陽花(アジサイ)の特徴と飾り方|雨の季節に淡い色の花を咲かせる枝もの

紫陽花(アジサイ)の基本情報
| 植物名 | 紫陽花(アジサイ) |
| 学名 | Hydrangea macrophylla |
| 英名 | Hydrangea |
| 別名 | 七変化、八仙花 |
| 科目/属性 | アジサイ科/アジサイ属 |
| 分類 | 落葉低木 |
| 原産地 | 日本、東アジア |
| 流通時期 | 5~7月 |
| 流通量 | ★★★★★ |
| 持ちのよさ | ★☆☆☆☆ |
※★は5段階です
紫陽花の特徴
紫陽花は、アジサイ科アジサイ属の落葉低木。小さな淡い色の花が寄り集まって咲き、ひとつの大きな花のように見えるのが特徴。梅雨の時期に色鮮やかな花を咲かせることから「雨の似合う花」として親しまれています。
日本に自生するガクアジサイが西洋に渡って品種改良が重ねられ、西洋アジサイとして逆輸入されたのだそう。
土壌の酸性度によって青やピンク、紫など異なる花の色を楽しめるのも魅力のひとつです。
開花時期は5月から7月と梅雨の時期に重なり、しっとりとした雨の中で一層鮮やかに輝きます。本格的な夏が始まる前の、雨の季節の訪れを告げる花として愛されています。

紫陽花の花言葉
紫陽花の花言葉には「移り気」「無常」「辛抱強い愛」「家族団らん」などがあります。花言葉は、興味深いエピソードが由来してつけられていたり、花姿そのものを表していたりしますよ。
「移り気」「無常」
一見ネガティブなように聞こえる花言葉たちですが、これは土壌によって色が変わることから、まるで気持ちが揺れ動く様子を連想させたことが由来とされています。
特に咲き始めから時間とともに色合いが変わっていく姿は、自然の中の「七変化」としても知られ、紫陽花の別名としても親しまれています。
このような特性が、まさに「移り気」を象徴する花言葉を形作っているのですね。
「辛抱強い愛」
紫陽花が長い期間美しく咲き続けることから、「辛抱強い愛」という花言葉がつけられました。
この花言葉は、困難な状況でも大切な想いを貫く姿を象徴しているのかもしれません。
「家族団らん」
小さな花がたくさん寄り集まり、大きな一つの花のように見える紫陽花。その姿が、家族が一つにまとまって過ごす温かさをイメージさせ、「家族団らん」の花言葉が生まれました。
紫陽花の花言葉は、その花姿や特性から生まれたもので、人々の絆や感情をイメージさせるものが多いですね。
紫陽花の飾り方

紫陽花の飾り方としては、その特有の丸みとボリュームを活かすのがポイントです。
花器の形は、幅広で丸みのあるものや高さの低いものがおすすめです。紫陽花の自然な広がりを楽しむため、口が広めの花器を使うと綺麗にまとまるでしょう◎
花器と紫陽花の枝の長さの比率は、1対1.5から1対2程度が理想的です。これにより、全体のバランスが良くなり、自然な雰囲気を演出できます。
柔らかい花色と紫陽花特有の質感が、空間に癒やしを与えてくれます。ぜひ、季節感を取り入れながら飾ってみてくださいね。

Flora | デンマーク王室御用達ブランドの名作花器
商品をみる 〉
花器に生ける時の注意点
花器に生ける際に気を付けるポイントは、まず枝が長すぎる場合は花器に合わせて切ることです。長いままで飾ってしまうとバランスが悪くなったり、枝が広がりすぎてまとまりにくいことがあります。
水につかる枝の断面に切り込みを入れると、水に触れる面積が広くなり、水の吸い上げが良くなります。 花瓶に入れる水の量は枝の3分の1がつかる程度にして、こまめに取り替えましょう。
枝の切り込みを入れる際には、枝ものや花木用の剪定鋏を利用するのがおすすめ◎剪定鋏を選ぶコツは、自分の手に合ったサイズを選ぶことです。

外山刃物 | 太枝も切れる、一生ものになる剪定ばさみ
商品をみる 〉
紫陽花のお手入れ方法
紫陽花はその特性を把握して丁寧にお手入れすれば、美しさをより長く楽しむことができます。今回は、枝ものの基本的なお手入れ方法をご紹介します。
基本のお手入れ
1. お受け取り当日の切り戻し

届いたその日のうちに切り戻しを行い、花器に飾るのがおすすめです。切り口には十字の切り込みを入れ、木皮を剥ぐことで水分の吸収が促進されます。
さらに、延命剤を使用した水を使えば、水が清潔に保たれ、花の鮮やかな色をより長く楽しめますよ。
枝ものの美しさを、より長く堪能するためのひと工夫ですね◎
■枝ものを長く愛でるための、鮮度保持剤

花枝に必要な栄養を与え、花器のお水を清潔に保つために、鮮度保持剤を取り入れてみては?切り口の樹液を溶かして水上がりをよくする効果があり、枝ものをより長く楽しめます。
枝もの専用鮮度保持剤はこちらから。
■水上がりを良くするフローリストナイフ

水に浸かる部分の木皮を剥くことで、水上がりをよくしてくれるVICTORINOX(ビクトリノックス)社製のフローリストナイフはこちらから。
世界中のプロが愛用する確かな品質です。
2. 枝ものにとって心地よい場所を選ぶ
枝ものは、エアコンの風があたらない、涼しくて通気性の良い場所が理想的です。
リビング、玄関、キッチンなど、どこに置いても空間の雰囲気をガラッと変える力を持っていますので、直射日光を避けて、枝ものが快適に過ごせる場所を選んでください。
また、寝室や洗面所など静かで落ち着いた空間に飾るのもおすすめです◎
3. こまめな水替え

水は濁ってしまう前にこまめに交換しましょう。その際に、茎の切り戻しもするとまた水を吸いやすくなります。
その茎にあるぬめりを取り除いたり、茎を斜めに切るなど、少しの工夫が美しい状態を保つ助けになります。
それでも枝ものの元気がない時は…
短く切って、小分けにして楽しむ

日々のお手入れをしていても、日が経つことで、どうしても少しずつ水が上がりにくくなっていきます。そんなときは、思い切って短く切り分けてしまうのもいいでしょう。
短くなることで水が上がりやすくなりますし、小さな花器に生ければまた新鮮な感覚で枝ものを堪能できますよ。
紫陽花の豆知識

色が土壌で変化
紫陽花は、花の色が土壌の性質によって変化することがよく知られています。
酸性の土壌では、紫陽花の根がアルミニウムを吸収し、その化学反応が青色の花を咲かせます。反対に、アルカリ性や中性の土壌ではアルミニウムの溶解が難しく、ピンクや赤色の花が咲く仕組みです。
この色の変化が起こる原因は、紫陽花が持つ色素「アントシアニン」で、アルミニウムと結びつくことで青色を発現する性質があります。
日本は雨が多く、酸性の土壌が自然に形成されやすいと言われています。青紫色の紫陽花をよく見かけるのは、そのためですね。
シーボルトが名付けた紫陽花
シーボルトは1823年に出島へオランダ商館の医師として来日し、日本の植物に深く魅了されました。
その中でも特に美しい紫陽花に、恋人である楠本滝(お滝さん)の名前を付けました。彼はその花を「Hydrangea otaksa(オタクサ)」と名づけ、西洋に紹介したのです。
「オタクサ」という名前は正式な学問的には無効とされましたが、その愛の物語は長崎などで今も語り継がれ、実際に紫陽花は「オタクサ」や「お滝さん花」として親しまれているそうです。
このエピソードは長崎の文化に深く根付いており、「長崎オタクサ祭り」という紫陽花のお祭りまで開催されています。
紫陽花のまとめ

紫陽花(アジサイ)は、梅雨の時期に色鮮やかな花を咲かせることから「雨の似合う花」として親しまれています。その丸い花房が特徴で、小さな花が集まることで生まれるボリューム感が、どこか愛らしさを感じさせます。
また、土壌が酸性だと青色、アルカリ性だと赤色に変わる特徴があります。
花言葉には「移り気」「無常」「辛抱強い愛」「家族団欒」などがあり、その色の変化や、花姿からイメージされる人々の絆や温かい思いを表現しています。
梅雨の季節に一足早く夏の訪れを感じさせてくれる植物として、人々に愛される紫陽花。ジメジメした空気を吹き飛ばす、淡い色が爽やかな紫陽花の枝ものを、ぜひ飾ってみてくださいね◎

【SiKiTOのよみもの】枝もの図鑑
よみもの一覧をみる〉

枝もの定期便|自宅で待つだけ、飾るだけ。
商品をみる 〉
PRODUCTS