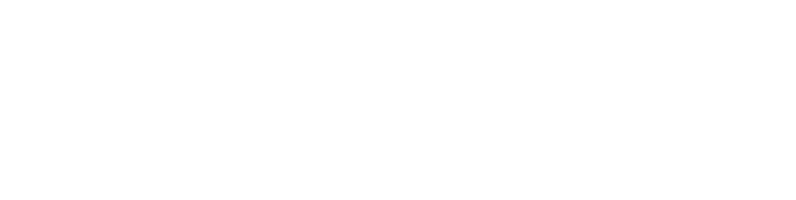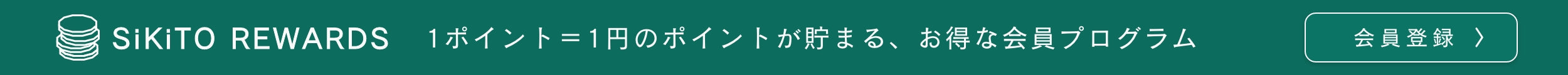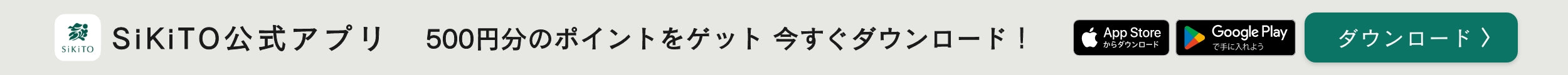【二十四節気】
大暑(たいしょ)

大暑(たいしょ)
7月23日〜8月6日頃
一年のうちでもっとも暑さが厳しいとされる「大暑(たいしょ)」。暦の上では夏の最後の節気です。
高い空に蝉の声が響き渡り、陽の光が容赦なく地上を照らし続ける夏の頂点とも言える時期。子どもたちにとっては待ち詫びた夏休みが始まり、全国各地で花火大会や夏祭りが開催されます。
猛暑に負けない体力をつけるための「土用の丑の日」もこの時期です。
七十二候
7月23日〜27日頃「桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)」

桐の花が実を結びはじめる頃。
春に咲いた薄紫の花が夏の日光を浴びながら少しずつ実をふくらませていきます。桐は古くから「吉兆の木」とされ、家紋や伝統装飾にも用いられてきました。
桐の枝は、秋の枝ものとしても流通します。数は比較的少ないですが、ベージュのベルベットのような個性的な姿が特徴的です。
7月28日〜8月1日頃「土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)」

土が湿るほどの蒸し暑さが本格化する頃。
地中には熱と湿気がこもり、日が昇れば気温はぐんぐん上がり、湧き立つような熱気に包まれる様子はまさに「盛夏」。
身体にとってはつらい時期でもありますが、稲や野菜の生育にとっては大切なエネルギー源。蒸し暑いからこそ育まれる夏の豊かさもあるのですね。
8月2日〜6日頃「大雨時行(たいうときどきふる)」

夕立や雷雨が突然訪れる頃。
急に空が暗くなり、激しい雷雨が訪れる夕立は昔から夏の風物詩です。強い日光で乾いた地面を潤し、空気を入れ替えてくれるような雨。
雨が上がると気温も和らぎ、土と草の匂いがふんわり立ちのぼります。大自然が深呼吸しているように感じられる瞬間です。
旬の味わい、行事など
大暑の頃の慣わしといえば、鰻を食べる「土用の丑の日」。

栄養豊富な鰻は夏バテ気味の体力や食欲を取り戻すための知恵として親しまれてきました。鰻のほかにも、「う」のつく食べ物として梅干し、うどん、瓜などを食べて暑気払いする風習もあったそう。

果物では桃やスイカが旬。きりっと冷やした果実の甘みが、乾いた身体に心地よく染み入ります。
「大暑」まとめ
大暑は、自然が力の限りを尽くして生命を育む季節。
その圧倒的なエネルギーは近年では猛暑、酷暑と呼ばれ生命の危険を感じることすらあります。
暑さと上手に付き合いながら、時には夏ならではの陽炎を見つけたり、蝉しぐれに耳を傾けたりする瞬間も楽しみたいものです。
大暑をすぎると立秋。厳しい残暑の中でも暦のうえではもう秋となります。
PRODUCTS