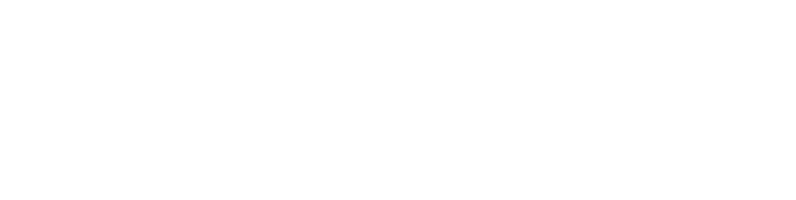蝋梅(ロウバイ)の特徴と飾り方|寒い冬に、蝋細工のような黄色い花を咲かせる枝もの

蝋梅(ロウバイ)の基本情報
| 植物名 | 蝋梅(ロウバイ) |
| 学名 | Chimonanthus praecox |
| 英名 | winter sweet、Japanese allspic |
| 科目/属性 | ロウバイ科/ロウバイ属 |
| 分類 | 落葉/低木 |
| 原産地 | 中国 |
| 流通時期 | 12~1月 |
| 持ちのよさ | ★★★☆☆ |
| 流通量 | ★★☆☆☆ |
※★は5段階です
ロウバイの特徴
ロウバイ科ロウバイ属の落葉低木。名前のとおり、ロウ細工のような質感の黄色い花が新春に咲き誇ります。なにより特徴的なのが、その清潔で甘い香りです。四大香木(こうぼく)のひとつとして数えられています。
風水の世界では、全体運や金運がアップするとも言われ、お守り的な存在でもあります。原産地である中国では、ウメ、スイセン、ツバキとともに「雪中四友(せっちゅうしゆう)」と呼ばれ、雪の中で咲く美しい花の代表として尊ばれています。
日本には江戸時代初期に渡来し、生け花や茶花、庭木として愛されてきました。もとのロウバイの花は内側の花弁が茶褐色ですが、一般に出回っているのは、すべての花弁が黄色のソシンロウバイです。

ロウバイの花言葉
ロウバイの花言葉には「奥ゆかしさ」「慈愛」「先見」などがあります。
「奥ゆかしさ」「慈愛」
「奥ゆかしさ」という花言葉は、まだ厳しい寒さの冬にいち早く静かに花を咲かせるその姿に由来しています。また、うつむくように咲く様子からは控えめで奥ゆかしさが感じられ、それが花言葉の背景となっています。
「先見」
雪の降る時期に咲く貴重な花として親しまれているロウバイ。「先見」という花言葉は、冬に咲くそのめずらしい性質から、春の訪れを予兆する花としてのイメージに結び付いています。
寒い冬に鮮やかな黄色い花を咲かせ、見る人々に希望や優しさを届けるロウバイは、その健気な様子が花言葉に由来したようですね。
ロウバイの飾り方

ロウバイを飾る際には、その控えめで上品な雰囲気を生かすため、シンプルで色味の少ない花器を選ぶと相性が良いでしょう。
ロウバイだけで花器に挿しても美しいですし、花だけお皿に浮かべたりしてもきれいです。
またロウバイは、茶花や生け花としても早春の花材として欠かせない存在です。アレンジに使うときは、キク、スイセンなどと合わせて和の雰囲気にすることもできますし、ガラスの花器を使用して洋風にも使うことができます。

TONE | 凛とマットな磁器製枝もの花器
商品をみる 〉
花器に生ける時の注意点
花器に生ける際に注意したいのは、全体のバランスを考えて花器に合わせて切ることです。長いままで飾ってしまうと枝が広がってしまったり、フラワーベースが倒れやすくなってしまうことがあります。
茎の最下部から2~3センチのところを斜めに切る「水揚げ」もやってみてください。このひと手間を加えると、茎の水に触れる面積が広くなり、枝ものがより長持ちすることが期待できますよ。
枝ものや花木専用の剪定鋏を使って枝の切り込みを入れてみましょう◎

外山刃物 | 太枝も切れる、一生ものになる剪定ばさみ
商品をみる 〉
ロウバイのお手入れ方法
ロウバイは、冬季に香りのよい花をつけるため庭木にもよく利用される枝ものですが、時に蕾やお花がポロっと落ちてしまうこともあるので気を付けて扱いましょう。そのほかにも、より長くロウバイの枝ものを楽しむためには、ちょっとした日々のお手入れが大切◎
今回は、初心者の方にも簡単にできる、枝ものの基本的なお手入れ方法をご紹介します。
基本のお手入れ
1. お受け取り当日の切り戻し

届いた当日のうちに、切り戻しをしてから花器に生けましょう。切り戻しとは、茎の下の方を切り植物の成長を促進することを言います。
その際、根本に十字の切り込みを入れ、さらに木皮を少し剥いてあげると、より水を吸いやすくなります。
枝ものをより長く楽しむために、水に延命剤を入れるのもよいでしょう。花瓶の水が汚れるのを防いだり、花の色を鮮やかに保つ効果などがありますよ。
■枝ものに栄養を与える、鮮度保持剤

花枝に必要な栄養を与え、花器のお水を清潔に保つ鮮度保持剤。少しでも長く枝ものを楽しみたいあなたにおすすめ◎
切り口の樹液を溶かして水上がりをよくする効果があり、枝ものを長生きさせる効果が期待できます。
枝もの専用鮮度保持剤はこちらから。
■水をより吸収させるための、フローリストナイフ

切り戻しをする際に、水に浸かる部分の木皮を剥くことで、植物がより水を吸いやすくなり、枝ものが長持ちする効果が期待できます。
木皮を剥くには、専用の切れ味の良いナイフを使うのがオススメ。VICTORINOX(ビクトリノックス)社製のフローリストナイフは、こちらからチェックしてみてください。
世界中のプロが愛用する確かな品質です。
2. 枝ものにとって心地よい場所に飾る
枝ものは、エアコンの風が直接当たる場所は避けましょう。風通しが良く涼しい場所に置くのが適しています。
寒さにも強いので、玄関前などの戸外に置いても問題ありません。直射日光を避けて、枝ものの心地いい場所に飾ってみましょう。
リビングはもちろん、玄関やキッチン等どこに置いても空間の印象を変える存在感があります。寝室や洗面所に飾るのもおすすめです◎
3. こまめに水替えを行う

水は濁ってしまう前にこまめに交換しましょう。
枝もののために開発された花器、EDA VASEなら、ベースの部分がガラスよりも軽くて丈夫なポリカーボネート製なので、水替えもお手軽です。
それでも枝ものの元気がない時は…
短く切って、違った雰囲気を楽しもう

枝ものは比較的長持ちするものが多いですが、日が経つと、どうしても少しずつ水が上がりにくくなっていきます。少し枝ものの元気がなくなってきたと感じる時は、思い切って短く切り分けて飾ってみては。
短くなることで水を吸収しやすくなりますし、小さな花器に飾ると、また違った楽しみ方ができますよ♪
ロウバイの豆知識

冬の象徴としてのロウバイ
ロウバイは、和歌や俳句の中で冬の象徴として詠まれることが多い植物です。冬の季語としてもよく知られ、その美しい黄色い花と甘い香りは、厳しい寒さの中で希望や忍耐を象徴する存在として、多くの詩人や文人に愛されてきました。
かの有名な芥川龍之介も、このような一句を詠んでいます。
ー蝋梅や 枝まばらなる 時雨ぞら
(蝋梅の花が咲いている枝はまばらで、その上に時雨が降る空が広がっている。)
この句では、ロウバイの美しさと共に、冬の静けさや儚さが表現されています。ロウバイは「雪中四友」の一つとしても知られ、雪の中で咲く4つの花の一つとして、和歌や文人画の題材にされてきました。
ロウバイはその名前や花の特徴から、和歌の中で季節感を表現する重要な役割を果たしており、冬の情景や感情を詠む際に欠かせない存在となっています。

ロウバイの名とその由来
蝋梅(ロウバイ)の名前にはいくつかの由来があり、それぞれがその特徴や魅力を伝えています。
まず、中国では「蝋梅(ラーメイ)」と呼ばれ、それを日本語読みしたものが「蝋梅」という名前になっています。また、花びらの質感や光沢が蝋でコーティングしたようにつやがあってしっとりしており、蝋細工を思わせることから、この名前が付けられたとも言われています。
さらに、ロウバイは陰暦12月の「朧月(ろうげつ)」に咲くことに由来しているという説もあります。
また、英語では“Winter sweet”と呼ばれ、甘い香りを放ちながら冬の寒さの中で咲く様子を見事に表しています。
こうした様々な名前の由来には、ロウバイの外見だけでなく、その香りや咲く季節といった、多面的な魅力が込められているのですね。
ロウバイのまとめ

ロウバイ科ロウバイ属の落葉低木。ロウ細工のようなつやっとした質感の黄色い花が、まだ寒い時期の新春に咲き誇ります。その特徴的な甘い香りも、魅力のひとつです。
ロウバイは、ウメ、スイセン、ツバキとともに「雪中四友(せっちゅうしゆう)」と呼ばれ、雪の中で咲く美しい花の代表として愛されてきました。
花言葉は、「奥ゆかしさ」「慈愛」「先見」など。
寒い冬に鮮やかな黄色い花を咲かせ、見る人々に希望や優しさを届けるロウバイ。その健気な様子が、花言葉にぴったりですね◎

【SiKiTOのよみもの】枝もの図鑑
よみもの一覧をみる〉

枝もの定期便|自宅で待つだけ、飾るだけ。
商品をみる 〉
PRODUCTS