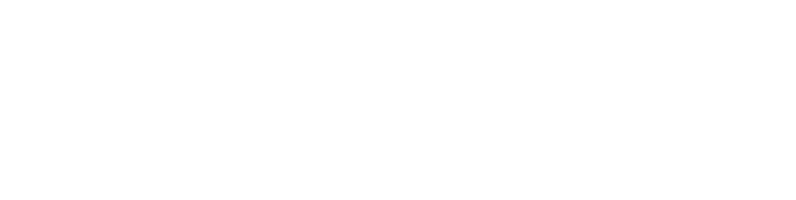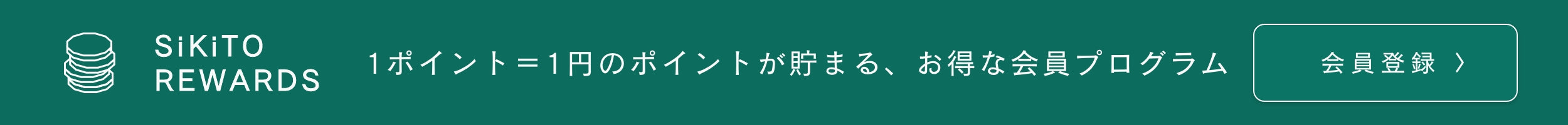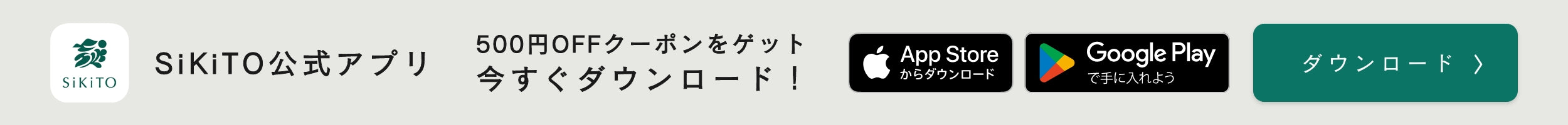【二十四節気】
処暑(しょしょ)

処暑(しょしょ)
8月23日〜9月7日頃
「暑さが処(おさ)まる」と書いて処暑。立秋を過ぎてもジリジリ続く残暑がようやく落ち着きはじめるとされる頃です。
昼間の陽射しはまだ強いものの朝夕の風はしだいに冷たさを含むようになります。夜には草むらから虫の声が聞こえ、心地よい秋の雰囲気を感じさせます。
夏空を象徴する入道雲はいつの間にか姿を消し、うろこ雲やいわし雲が広がるように。今年も残すところ約3分の1となります。
七十二候
8月23日〜27日頃「綿柎開(わたのはなしべひらく)」

綿の実を包む萼(がく)が開き、中から白い繊維が顔をのぞかせる頃。ふくらんだ綿花は秋風によって乾かされたあとに収穫されます。
まだ遠いと思っていた寒い時期が確実に近づいてきていることを示す、小さなしるしのひとつです。
8月28日〜9月1日頃「天地始粛(てんちはじめてさむし)」

暑さが和らぐ時期。「粛」は和らぐ・弱ることを意味します。
近年は残暑が厳しく、名の通りに涼しさを感じられる日ばかりではありませんが、夕暮れに立つ風の質感や夜空の星の輝きの澄み具合に、少しずつ秋の訪れが感じられるはずです。
9月2日〜9月7日頃「禾乃登(こくものすなわちみのる)」

田んぼの稲穂が黄金に色づき、頭を垂れはじめる頃。
風に揺れる稲穂の波は、秋の豊穣を約束する風景です。稲作を中心に暮らしてきた日本人にとっては特別な意味を持ち、収穫の喜びへの期待がふくらむ時期でもあります。
旬の味わい、行事など
夏の名残と秋のはしりが同居する豊かな季節です。
なす・きゅうり・ピーマンなど夏野菜がまだ盛りを見せる一方で、里芋やさつまいも、かぼちゃなど秋の食材が顔を出しはじめます。

果物では、いちじくやぶどう、梨が旬を迎えます。水分をたっぷり含んだ果実は、暑さで疲れた体に心地よく染み渡ります。
魚では、秋の魚の代名詞的存在である「秋刀魚(さんま)」が並ぶ時期。シンプルに塩焼きでいただくのが格別です。

地域によっては季節行事として「地蔵盆(じぞうぼん)」が行われ、子どもの健やかな成長を願う祭りとして親しまれています。
また、旧暦の7月15日を中心とした「盆の名残」の風習が残る土地もあり、人々が季節の巡りとともに祈りを捧げてきたことが伝わります。
「処暑」まとめ
処暑は、ようやく夏の終わりを実感できるようになる時期です。
昼は汗がふきだすほどの暑さながらも、ふと吹く風や虫の声に気づくと季節の変化に気づくことができます。
夏の疲れが出やすい頃でもあります。暑い屋外と冷えた室内との温度差や、冷たいものばかりで弱った身体を労わってあげましょう。
いちじくのコンポートや、しょうがを添えた焼きなすなどは、この時期の身体にじんわりと染み込むような滋味深さがあります。ほんの小さな台所の工夫が、次の季節を健やかに迎える力を育んでくれます。
PRODUCTS