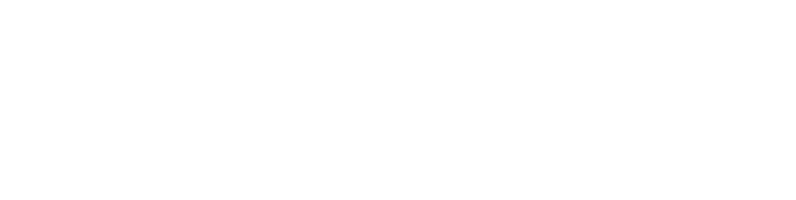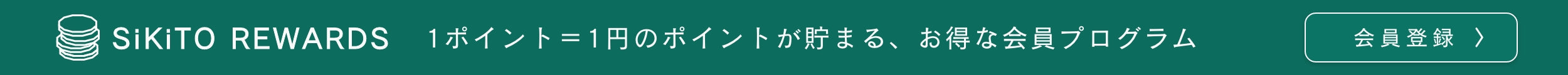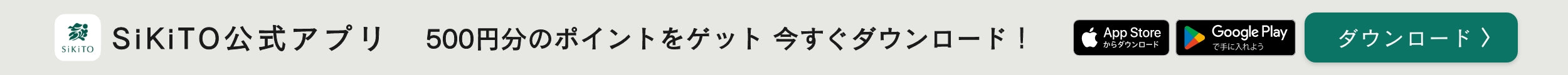「枝もの」の飾り方|プロが教える、おしゃれなアレンジテクニック&コツ

がさっと無造作に生けてもサマになる枝もの。でも今日の姿はなんとなくしっくりこない…そんなことはありませんか?
すぐに取り入れられて一生使えるテクニックを、枝もの定期便の立ち上げからお世話になっているフローリスト・岡 寛之(おか ひろゆき)さんにお聞きしました。
① 基本のバランスは「器1:枝1.5〜2以上」
はじめに、必ず使う花器と枝ものの基本バランスは「器1:枝1.5-2以上」がおすすめです。例えば30cmの高さの花器を使うのであれば、75-90cm以上の枝ものを生けると伸びやかかつ迫力のある仕上がりに。

② 偶数よりも奇数で心地よく
枝の本数は、偶数よりも奇数のほうが心地よくまとまります。
左右非対称で「三角形」をつくるように意識すると心地よいバランス感を見つけやすいです。

枝が2本しかないときは、思い切って左右どちらかに寄せてしまうほうがしっくりくることも。
③ あえて崩して心地よくまとめる
短めの枝がたっぷりあるときは、まっすぐ花器の底まで投げ込むよりも口径を使って傾けることでダイナミックな広がりが加わります。

切り口が浮くので、水に浸かっていることをしっかり確かめましょう
④ 野山での本来の様子を再現する
自然環境下での樹木は日光に向かって枝を伸ばし、日光に当たっていた面の色が濃くなるもの。太陽に向いていた面が「表」で、葉の色や枝の向きで見分けることができます。
裏向きで生けると不自然に見えてしまうので、ご自宅で生けるときにも本来の姿を再現してあげましょう。

⑤ EDA VASEは、あえてリングから外してみる
枝もの専用花器「EDA VASE」に複数本を生ける場合には、いくつかの枝をリングから外してあげるとふんわりと広がります。どこを正面とするか決め、ここでも三角形を意識しながら生けるのがポイントです。

EDA VASEを使ったアレンジテクニックは、以下の記事でもご紹介しています。

【枝もの専用花器】
EDA VASEのデザインとアレンジ
よみものはこちら 〉
⑥ ちょっとした小道具で、生け方はさらに広がる
生け花作品のような独創的なアレンジも、実はちょっとした小道具を使えばテクニック要らずで叶えられます。
枝ものの剪定でカットした小枝や古枝は、自由自在な枝留めに。

華奢な器のなかで枝ものを支えたり、突っ張り棒のように花器に挟み込めば「一文字留め」の要領で枝を狙った位置に決めることができます。


繊細な器を使う際は、力を加えすぎないようご注意を
より浮遊感のある生け方がこちら。背の低い器のなかにミニ剣山や丸めたワイヤーを仕込むことで、1本の枝だけでもすっと立ち上がります。

岡さんによるアレンジテクニックは、以下の記事でもご紹介しています。

【枝もの定期便イベント】
四季を感じる枝ものの集い〈2024早春・花見〉
よみものはこちら 〉
枝もの初心者の方でもすぐに実践できるテクニックの数々、いかがでしたか?
深めのお皿や酒器も花器として活躍してくれますし、ちょっとした技を使うことで小枝も美しく飾ってあげることができます。ぜひ一度お試しくださいね。
PROFILE | 岡 寛之 (おか ひろゆき)

広島の生花店での勤務の後、半年間デンマークへ留学。帰国後、フラワースクールや花の仲卸での勤務を経て、フリーランスに転身。
2013年7月、ベルギーのStiching Kunstboek社より発刊した初の単独作品集『HiroyukiOka MONOGRAPH』はヨーロッパ各メディアでも数多く取り上げられ、国内外から高く評価されています。

枝もの定期便|自宅で待つだけ、飾るだけ。
商品をみる 〉
PRODUCTS