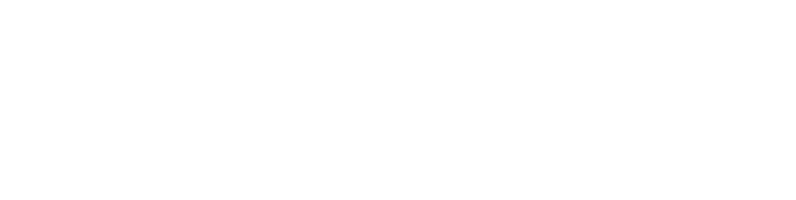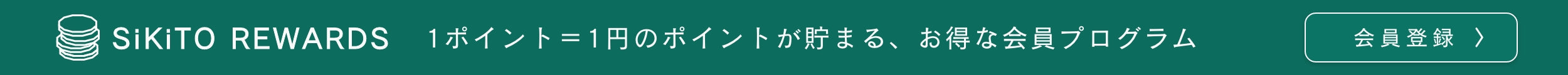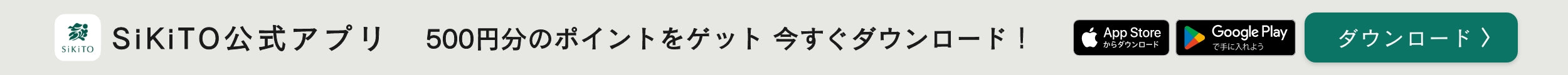小手毬(コデマリ)の特徴と飾り方|手毬のように小さな白い花をつける枝もの

小手毬(コデマリ)の基本情報
| 植物名 | 小手毬(コデマリ) |
| 学名 | Spiraea cantoniensis |
| 英名 | Reeves spirea |
| 別名 | スズカケ、テマリバナ、中国名は麻葉繡球 |
| 科目/属性 | バラ科/シモツケ属 |
| 分類 | 落葉/低木 |
| 原産地 | 中国 |
| 流通時期 | 1~3月 |
| 流通量 | ★★★★★ |
| 持ちのよさ | ★★☆☆☆ |
※★は5段階です
コデマリの特徴
バラ科シモツケ属の落葉性低木。コデマリは、その名のとおり小さな手毬を連想させるような小花のかたまりが、しなやかに垂れる枝にぎっしり並ぶ姿が美しい枝ものです。
中国から伝わり、江戸時代以降、観賞用として栽培されてきました。
可愛らしい花と清楚な枝の雰囲気が好まれ、一般家庭の庭木や切り花として利用される、春を代表する花木です。
また、遠くから見るとカスミソウを思わせる可憐で小さな花と、美しくしなる枝のラインが魅力的で、フラワーアレンジメントの主役にも脇役にもなれる人気の花材でもあります。
春に公園や庭の植え込みなどで、小さな白い花を咲かせたコデマリが見られるでしょう。

コデマリの花言葉
コデマリには「友情」「努力」「優雅」「上品」「いくじなし」という花言葉があります。
「友情」
3㎜程の白い小花が、雨風に負けずに寄り添って咲く様子を表したものです。その姿は、まるで手を取り合って助け合う友情の絆を思わせます。
「努力」
細い枝でありながら可憐なコデマリを支える姿や、コデマリの花を大きく見せるように、小花たちが集まって努力している姿からつけられたといわれています。
「優雅」「上品」
コデマリの白い小花の上品さ、また気品溢れる花姿が清楚な印象をイメージさせることからつけられたといわれています。その様子は、白いヴェールにつつまれた花嫁を彷彿とさせるようなエレガントさが感じられますね。
「いくじなし」
小花が寄り添うようにして鞠のような花のかたまりをつくっているのが特徴のコデマリ。この花言葉の由来についての詳細は不明ですが、一輪ずつ咲くのではなく、集まらないと咲くことができない=「いくじなし」と結びついたのでは、と言われています。
「友情」「努力」という花言葉から、発表会やスポーツ大会、大事な試験などを控えた友人にメッセージを添えて贈るのもおすすめ◎
「優雅」「上品」は気品や美しさを表すので、新郎新婦や大切なパートナーへのギフトにもピッタリです。
ただし、コデマリには「いくじなし」というネガティブな花言葉もあるので、贈る際には温かな言葉を添えると良いでしょう。
コデマリの飾り方

ひとつひとつの花は小さいけれど、その小さな花が集まって手毬のような丸い形を作るコデマリ。たくさんの手毬がポンポンと咲き誇り、枝が弓なりにしなる様子も魅力的です。
飾る際には、花向きを考えながら左右に流れるように花器に入れていきます。枝の流れに表裏があるので向きを生かしてバランスを整えましょう。
花がたくさんついているので意外と重さのあるコデマリ。大きい枝ごと活けるなら、安定感と重さがある花器を選ぶのがおすすめ。
EDA VASEは、スリムでコンパクトながらも、高さのある枝をしっかりと支えることができる設計になっています。コンクリート製台座の重さは約4kgあり、しっかりとした安定感で、初心者の方でもお手入れや水替えがしやすいのでおすすめです◎

▶EDA VASE | 枝ものを美しく飾る、コンパクトな花器
商品をみる 〉
コデマリを飾ったインテリア例
枝ものは、お部屋に飾るだけで、同じインテリアでもガラッと雰囲気を変えることができるのが魅力ですよね。
コデマリは、真っ白な小花と葉のグリーンの調和を楽しめる枝もの。ダイニングテーブルの上に豪華に飾ったり、リビングルームのフロアに大きめの花器を置いて生けてみたり。和洋どんなインテリアにも自然に馴染み、存在感を放ってくれます。
家にある大小さまざまなデザインの花器に合わせて切り分けて飾るのもおすすめですよ。
花器に生ける時のお手入れ
花器に飾る際の注意点は、こまめに水替えを行い、花瓶を清潔な状態に保つこと。 その際、茎を切り口を切る「切り戻し」を行うことで、切り口が新鮮になり水上がりがよくなります。
コデマリは比較的水が下がりやすい枝ものでもあるので、定期的に切り戻しを行いましょう。葉が多いままだとさらに水が下がりやすくなるので、ある程度整理してあげるのがおすすめです。
また、枝に付いている花が水に浸からないよう、下の方の花を取り除いてから生けるのも大切なポイントです。花が水についたままだと、花器の中で水質が悪化し、菌が増える原因になります。

外山刃物 | 太枝も切れる、一生ものになる剪定ばさみ
商品をみる 〉
コデマリのお手入れ方法
ご紹介した通り、コデマリは比較的水の下がりやすい枝もの。少しでも長く楽しむには、日々のお手入れが大切です。今回は、枝ものの基本的なお手入れの方法をお伝えします。
基本のお手入れ
1. お受け取り当日の切り戻し・水揚げ

枝ものをお受け取りいただいた当日のうちに、切り戻しをしてから花器に生けましょう。切り戻しとは、伸びすぎた茎や枝を短く切り詰めて、植物を若返らせる方法です。
合わせて、根本に十字の切り込みを入れ、ナイフを使って茎の表面の皮を削るように剥きます。その際、水に入る吸い上げ部分のみを削る事がポイントです。
また、水質を保つテクニックとして、鮮度保持剤を入れた水に生けるのもひとつの方法です。
■水質を保つ、オリジナル鮮度保持剤

SiKiTOが枝ものに最適な成分バランスで作った、オリジナル鮮度保持剤。花枝に必要な栄養を与え、花器のお水を清潔に保つ作用が期待できます。樹液溶解成分も配合し、樹液によって水上がりが悪くなってしまう枝もの特有の問題にも効果あり◎
枝もの専用鮮度保持剤はこちらから。
■水上がりを良くするフローリストナイフ

切り花の茎をカットするためのフローリストナイフは、枝ものの木皮を剥くのにも役立ちます。水に浸かる部分の木皮を剥くことで、水上がりをよくしてくれるVICTORINOX(ビクトリノックス)社製のフローリストナイフはこちらから。
2. 枝ものを適した場所に飾る
コデマリは日当たりと風通しの良い環境を好みます。南向き、または東向きの場所に飾ると元気に育ってくれるでしょう。夏は強い日差しを避けるため、適度に日陰のある場所が◎
空調が直接当たると乾燥が原因で調子を崩したり、花付きが悪くなったりしますので、注意しましょう。

3. こまめに水を替える

水は濁ってしまう前にこまめに交換するのをおすすめします。その際に切り戻しもすると、また水を吸いやすくなります。
ぬめりがある部分があれば、手で優しく擦り落としましょう。
枝ものの元気がない時は…
短く枝をカットして、小分けにして楽しむ

日が経つことで、少しずつ水が上がりにくくなっていきます。そんなときは、思い切って短く切り分けて飾ってみるのも良いかもしれません。
また、咲き終えそうなお花は先に摘み取ってあげるのもよいでしょう。花が落ちた後も、グリーンの枝ものとしてお楽しみいただけます。
丸みをおびたギザギザの葉は、花をつけている時とは違った魅力がありますよ。
工夫して、より長く枝ものを楽しんでくださいね。
コデマリの豆知識

さまざまな呼び名を持つコデマリ
コデマリは、中国から渡ってきた植物です。江戸時代頃から日本に定着し、栽培されるようになったとされています。
当初は「鈴掛(スズカケ)」と、呼ばれていたのですが、江戸時代初期頃から、白い小花がポンと丸くまとまって咲く様子がマリのようだと言うことで、「小手毬(コデマリ)」と言う名が広まったそうです。
古名の「鈴掛」は、弓なりにしなる枝にひとつひとつ花が咲く様子が、鈴を枝に掛けたように見えることが由来だとか。
他にも呼び名があり、花を団子になぞらえて「団子花(ダンゴバナ)」、花を手毬になぞらえて「手毬花(テマリバナ)」など、身近なものに例えられることが多かったようです。
この愛着の湧く可愛らしい呼び名からも、コデマリが永く人々に愛されてきたことがよくわかりますね。
コデマリの育て方
自然環境下での開花は4月から5月頃なので、温室を使った促成栽培によるものが1月頃から流通し、次第に季咲きと呼ばれる路地で自然に咲いたものも出回るようになります。
ちなみに、花器の水に食紅や染料を混ぜると花が淡く色づくので、少し遊んでみるのも面白いかと思います。
水が下がりやすいためこまめな切り戻しが必要です。穏やかな色合いの葉っぱとの調和も魅力ですが、葉っぱが多いと水が下がりやすくなるので、ある程度整理してもよいでしょう。
コデマリのまとめ

コデマリは春に咲くバラ科シモツケ属の落葉性低木。その名のとおり、小さな手毬を連想させるような小花のかたまりが、枝にたくさん並ぶ姿が美しい枝もの。
コデマリの花言葉は「友情」「努力」「優雅」「上品」「いくじなし」。小花が集まって咲く様子からつけられました。
可愛らしい花と清楚な枝の雰囲気が好まれ、一般家庭の庭木や切り花として利用される、春を代表する花木です。
その花姿は、「今年も春を迎えられてよかった」としみじみ思わせてくれる愛らしさです。

【SiKiTOのよみもの】枝もの図鑑
よみもの一覧をみる〉

枝もの定期便|自宅で待つだけ、飾るだけ。
商品をみる 〉
PRODUCTS