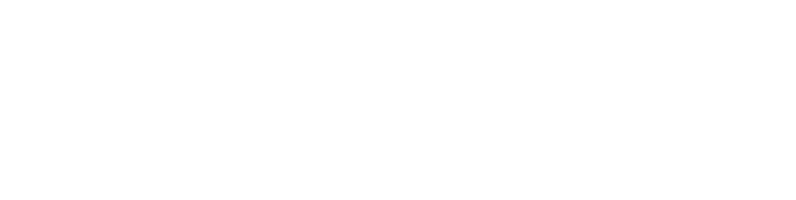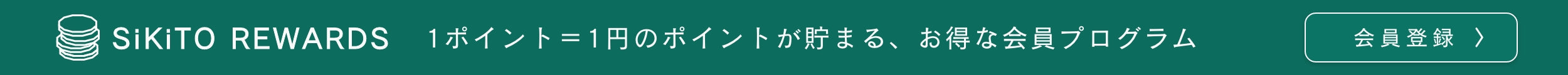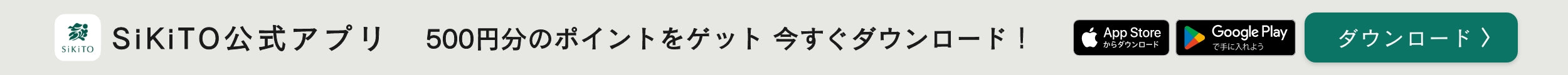雪柳(ユキヤナギ)の特徴と飾り方|枝に雪のような小さく白い花をつける枝もの

雪柳(ユキヤナギ)の基本情報
| 植物名 | 雪柳(ユキヤナギ) |
| 学名 | Spiraea thunbergii |
| 英名 | Thunberg's meadowsweet |
| 別名 | コゴメバナ、コゴメヤナギ |
| 科目/属性 | バラ科/シモツケ属 |
| 分類 | 落葉/低木 |
| 原産地 | 日本 |
| 流通時期 | 1~3月 |
| 流通量 | ★★★★☆ |
| 持ちのよさ | ★★★☆☆ |
※★は5段階です
ユキヤナギの特徴
バラ科シモツケ属の落葉性低木。ユキヤナギは、柳のように枝垂れる枝全体に、たくさん小さな花を咲かせる春の枝もの。その姿はまるで、雪が積もったかのように可憐で愛らしく、人々を魅了します。
日本が原産で、関東地方以西の本州、四国、九州にて、川岸の岩場などで野生のユキヤナギが見られます。一方で、自生するユキヤナギは少しずつ減ってきているといわれ、石川県ではユキヤナギの自生種が絶滅危惧種に指定されているほどです。
雪のような、控えめな美しさを感じさせるユキヤナギはひときわ目を引き、開花時期には公園などの植え込みを真っ白に変えます。その様子はまるで雪景色のよう。
群生しているとより見ごたえのあるユキヤナギ。しなるような枝が風にゆらゆらと揺れる様子は、優雅で、風情が感じられます。

ユキヤナギの花言葉
ユキヤナギには「愛らしさ」「気まま」「殊勝」「静かな思い」という花言葉があります。
「愛らしさ」
ユキヤナギの花は1cmにも満たない大きさ。その小さい花がたくさん集まって一生懸命咲いている愛らしい様子からつけられました。
「気まま」
細くしなやかな枝が枝垂れて風にゆらゆらと揺れる様子、またランダムに枝を伸ばす自由気ままな様子を表しています。
「殊勝」
「殊勝」とは、素晴らしい、立派な、また、真面目に取り組む健気な様子を表します。ユキヤナギが健気に小さな花をたくさん咲かせる様子から、つけられました。
「静かな思い」
そのおしとやかで上品な様子が「静けさ」を思わせることから。決して派手ではないですが、静かに内に秘める美しさも感じられますね。
これらの花言葉から、優雅で、派手ではないけれど静かに内に秘めるような魅力を持ったユキヤナギが、より愛らしく感じられますね。
ユキヤナギの飾り方

枝ものはお手入れが簡単で丈夫な種類も多いため、インテリアグリーン初心者の方にもおすすめです。
大きく伸びる枝にたくさんの小さな花をつけるユキヤナギ。長い枝を活かして高さのある花器に生ければ、インパクトがありつつも上品な印象に◎
EDA VASEは、細身でコンパクトでありながら、背の高い枝をしっかりと支えることができるデザインとなっています。安定感があり、軽くて丈夫なポリカーボネート製の花瓶を採用しているので、初心者の方でも簡単に手入れや水替えができますよ。

ユキヤナギのひとつひとつの花は、1㎝にも満たない小さな小花。枝を短く切って、低い高さの花器に生けると、可愛らしいお花の印象が強くなります。
カットする長さや生ける花器によって雰囲気を変えられるのも、枝ものの魅力のひとつですね♪

EDA VASE | 枝ものを美しく飾る、コンパクトな花器
商品をみる 〉
ユキヤナギを飾ったインテリア例
枝ものは、自然の風合いと美しさをそのままインテリアに反映させることができます。枝の形状や花の色合いなどが部屋に自然なアクセントを加えます。
ユキヤナギは、しなる枝に咲く小花が雪のような可憐で美しい枝もの。そのまま飾るだけでも、細い枝が伸び美しく広がりを見せてくれます。
花器をリビングの床に置いたり、玄関ホールに置いたりして、よく目につくお気に入りのスペースを華やかに飾るのもいいですね。
花器に生ける時のお手入れ
花器に飾る際の注意点は、定期的に水替えを行い、花瓶をキレイに保つこと。 より花持ちを良くするためには、剪定鋏を使って茎の切り口に小さな割れ目を入れるのがおすすめ。この処理をすることで、水を吸いやすくなります。
また、枝に付いている花が水に浸からないよう、下の方の花を取り除いてから生けるのも大切なポイントです。花が水についたままだと、花器の中で水質が悪化し、菌が増える原因になります。
ちょっとした工夫を加えて、少しでも長くユキヤナギのお花を切り花で楽しみましょう!

外山刃物 | 太枝も切れる、一生ものになる剪定ばさみ
商品をみる 〉
ユキヤナギのお手入れ方法
枝ものを少しでも長く楽しむには、日々のお手入れが大切です。今回は、ユキヤナギをはじめとするよく流通している枝ものの基本的なお手入れの方法をお伝えします。
基本のお手入れ
1. お受け取り当日の切り戻し・水揚げ

枝ものは、届いたその日のうちに切り戻しをしてから花器に飾りましょう。
合わせて、根本に十字の切り込みを入れ、ナイフを使って茎の表面の皮を削るように剥きます。その際、水に入る吸い上げ部分のみを削るのがおすすめ。より水を吸いやすくなり、枝もののみずみずしさが長持ちします。
また、加えて鮮度保持剤を利用すれば、さらに枝ものの新鮮さを保つことが期待できます。
■オリジナル鮮度保持剤

SiKiTOが枝もののために理想的な成分バランスを研究してオリジナルで作り上げた、新しい鮮度保持剤です。この鮮度保持剤は、花や枝に必要な栄養を与え、花器の水を清潔に保つ効果が期待できます。
枝もの専用鮮度保持剤はこちらから。
■水上がりを良くするフローリストナイフ

切り花の茎をカットするためのフローリストナイフは、枝ものの木皮を剥くのにも役立ちます。水に浸かる部分の木皮を剥くことで、水上がりをよくしてくれるVICTORINOX(ビクトリノックス)社製のフローリストナイフはこちらから。
2. 枝ものを飾る場所の工夫
ユキヤナギは風通しと日当たりの良い、適度に湿気のある場所を好みます。窓際などの、明るいところに飾るといきいきと育ってくれるでしょう。
一方で、空調が直接当たると乾燥が原因で調子を崩したり、花付きが悪くなったりしますので、注意しましょう。

3. こまめな水替え

水は放っておくとすぐに濁ってしまいます。そうなる前に、定期的に水を交換するのをおすすめします。
茎にぬめりがある部分がある場合は、手で優しく擦り落としましょう。
それでも枝ものの元気がなくなったら…
短く枝を切り分けて、楽しむ

枝ものは比較的丈夫で長持ちしますが、それでも日が経つにつれ、少しずつ水が上がりにくくなっていくのは避けられません。
徐々に元気がなくなってきたかな…そんな風に見える時は、思い切って枝を短く切り分けて飾ってみてはいかがですか。
小さな花器に生け替えることで、違った印象を演出できますよ◎
より長く枝ものを楽しめるよう、工夫してみてくださいね。
ユキヤナギの豆知識

ユキヤナギとコデマリの違い
ユキヤナギとよく似ている花として挙げられるのが、コデマリ(小手毬)。同じ早春の時期に流通する、春の定番枝ものです。どちらも、バラ科シモツケ属の落葉低木であり、小さな白い花を咲かせる見事な花姿も似ているように見えます。
ふたつの植物の見分け方ですが、それぞれの名前がうまく特徴を表してくれています。
コデマリは、白い小花が集まって毬のように丸いかたまりを成すのに対し、ユキヤナギは、柳のような弓なりにしだれる枝に雪のようにたくさんの小花が咲き乱れます。
ちなみに姿がよく似ているオオデマリ(大手毬)は、バラ科ではなく、レンプクソウ科です。
いずれも春の季節を華やかに彩ってくれる、代表的な枝ものです。
ユキヤナギの学名は、シーボルトが名付け親
植物の学名の由来を深堀りすると、面白い歴史やエピソードに出会えることがあります。
ユキヤナギの学名は、Spiraea thunbergii(スピラエ・ツンベルク)。この名は、江戸時代後期に来日し蘭学を日本に伝えたドイツ人医師であり博物学者のシーボルトが名付けたそうなのです。
「Spiraea」(スピラエ)はギリシャ語で「螺旋」を意味し、ユキヤナギの葉がらせん状に付くことから名付けられました。
「thunbergii」(ツンベルク)は、江戸時代中期(1775~76年)に長崎・出島のオランダ商館に勤務していたスウェーデン人医師であり植物学者でもあるカール・ツンベルクにちなんでいます。
日本の歴史的にも有名なシーボルトは、江戸時代後期(1823~28年)に、政府の命令で来日し、オランダ商館に滞在していました。より早期に日本に渡来していた先輩のカール・ツンベルクに敬意を表して、その名前を命名したと言われています。
シーボルトの来日の目的のひとつは、蘭学者を育て、日本の動植物の研究をすること。滞在していた6年間、たくさんの植物を採集し、帰国後に日本の動植物に関する書籍もまとめました。著作「日本植物誌」の中で、ユキヤナギについて触れ、強い関心を示しています。
ユキヤナギの学名から遡って、シーボルトの半生や当時のオランダと日本の歴史に触れると、この可憐で儚げな白い花が、ずっと昔から日本に生息し愛されてきたことを、改めて感じられますね。
ユキヤナギの「根蒸し」
枝ものとしてのユキヤナギの栽培は福島県が盛ん。特に全国でも有数の産地である須賀川市では、他の産地とは異なり、出荷するユキヤナギを株ごと掘り起こし、ハウスで約2週間「根蒸し」を行っています。
「根蒸し」を行うことで、需要期に合わせて開花を調節することができ、出荷直前まで株が付いているため、開花後の花持ちが良くなるのです。
ただし、株ごと掘り起こすため大変な重労働となり、近年は出荷量が減少傾向にあります。
一年中楽しめるユキヤナギ
ユキヤナギは、枝ものとしては1~3月に多く流通します。硬い茎は水が下がりやすく、水をよく吸うため、こまめな切り戻しと水替えが必要です。
またユキヤナギは、可憐な白い花をたくさん咲かせる春の花として有名ですが、爽やかな印象の葉姿も人気があり、夏には青々しい葉ものとして、秋には紅葉ものとしても出回ります。
1年を通して季節の移り変わりを感じながら、その変化を楽しむことができるのも、ユキヤナギの魅力のひとつですね◎
ユキヤナギのまとめ

ユキヤナギは春に咲くバラ科シモツケ属の落葉性低木。
花言葉は「愛らしさ」「気まま」「殊勝」「静かな思い」。その愛らしい花姿や、自由に伸びる枝の様子などからつけられました。
伸びると枝垂れる枝に、小さな白い花をたくさんつけるその様子は、群生するとまるで雪景色のような美しさ。
ユキヤナギは、春は白く可憐な花、夏は青々とした緑、秋は紅葉と、1年を通して人々を魅了し続けます。
PRODUCTS